日本雑草学会
雑草分布状況全国調査(第4回)
ワルナスビ |
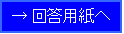
|
〈ご協力のお願い〉
日本雑草学会では,和文誌『雑草研究』の総説シリーズ「雑草モノグラフ」のための資料として,モノグラフ掲載種の分布情報をあつめています。2003年よりショクヨウガヤツリ,チガヤ,ミズアオイを対象に調査をおこない,多くの皆様からご協力をいただきました。
今回はワルナスビSolanum carolinenseをとりあげます。雑草学会会員の皆様はもちろん,植物や農業に関心をお持ちの会員外の皆様からの情報提供もお待ちしております。
調査結果は上記総説およびこのウェブサイトで紹介されます。同時に,情報をご提供いただいた皆様のお名前(もしくは機関名)を一覧として掲載し,お礼にかえさせていただきます。
|

国道沿いの植込み(福井県)
(写真提供:今泉智通氏)
〈ワルナスビについて〉
ワルナスビは栄養繁殖,種子繁殖いずれも可能な北米原産のナス科の多年草で,放牧地,飼料畑,植え込み等で普通にみられます。茎,葉柄,葉の主脈上に鋭い刺があり,茎葉や果実にアルカロイドが含まれるため,収穫物の汚染や作業妨害等の被害を引き起こします。
ワルナスビは輸入飼料等に付随して国外から種子が持ち込まれ,堆肥を介して定着すると考えられています。また,水平・垂直に広く深く拡がる根系および根の断片を通じた栄養繁殖を行うため,一旦はびこると防除が非常に困難です。被害および分布拡大阻止のため,適切な防除が必要ですが,既存の手段では困難なことが明らかになっています。様々な面から防除手段を開発する上で,現在の分布状況を把握することが必要です。皆様のご協力を宜しくお願いします。
|
|

飼料用トウモロコシ畑(三重県)
(写真提供:宮崎桂氏)
回答受付期限は2006年11月30日です。
和文誌編集委員会・雑草モノグラフ企画チーム
本調査に関する問い合わせ先
〒329-2793
栃木県那須塩原市千本松768
畜産草地研究所
黒川 俊二(和文誌編集幹事)
FAX: 0287-36-6629
E-mail: shunji@affrc.go.jp
|

白いタイプの花とトゲ
(写真提供:西田智子氏)

黄熟したワルナスビの果実
(写真提供:小畠辰三・裕子氏)
|
|
〈類似種との区別点〉
ワルナスビ
長さ約1cmの鋭いトゲが,葉脈の裏表,茎,花序軸にあります。6月ごろから直径約2.5cm,白〜淡紫色の花を房状につけます。果実は順次形成され,最大直径約1.5cm,球型で黄橙色に熟します。花は浅く5列するため,正面から見ると星型に見えます。
キンギンナスビ
葉の横幅が広めです。花冠の直径は約2cm,花弁は基部まで分かれます。果実は直径約2〜3cmで節間に1個ずつ着生し,球形,赤熟します。主に関東南部以西の暖地の海岸沿いに生育します。
イヌホオズキ類
一年草で,花冠および果実の直径は約1cm以内。果実は黒色です。トゲはありません。花弁が基部まで分かれます。
ヒラナス
食用ナスの台木として使われます。トゲが比較的まばらで,花冠の直径は約1.5cmです。果実は直径約3〜4cmで扁平な腰低のカボチャ型で赤熟します。
本州で多く見られるのはワルナスビおよびイヌホオズキ類ですが,堆肥から発生する雑草の分類は困難なことが多々あります。また,南方の地域では他の類似種も発生している可能性があります。同定が困難な場合は,乾燥させた植物体を新聞紙等に挟み,「本調査に関する問い合わせ先」までお送り下さい。なお,お送り頂いた標本は特に御要望がない限り,返却いたしません。
|
|
|
|
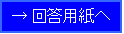 |